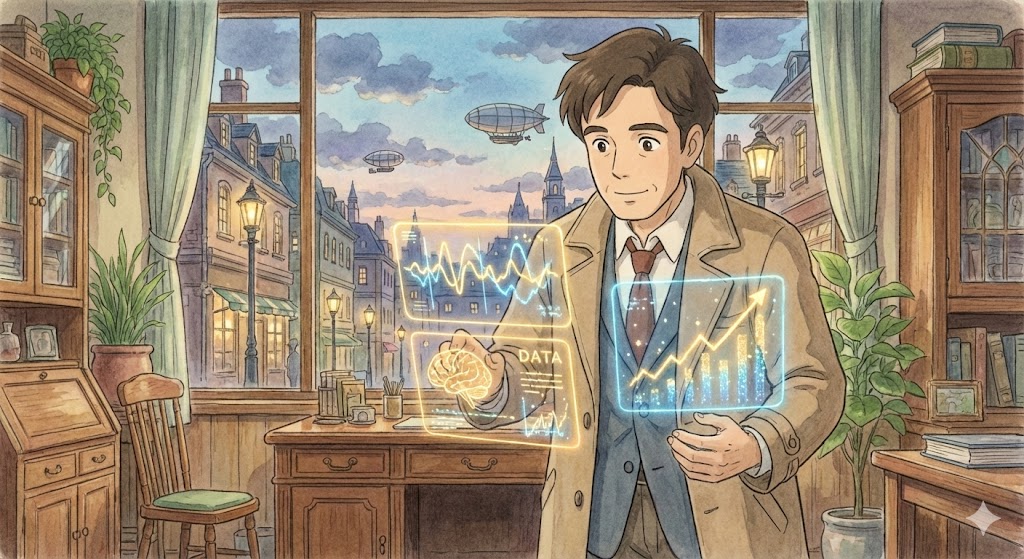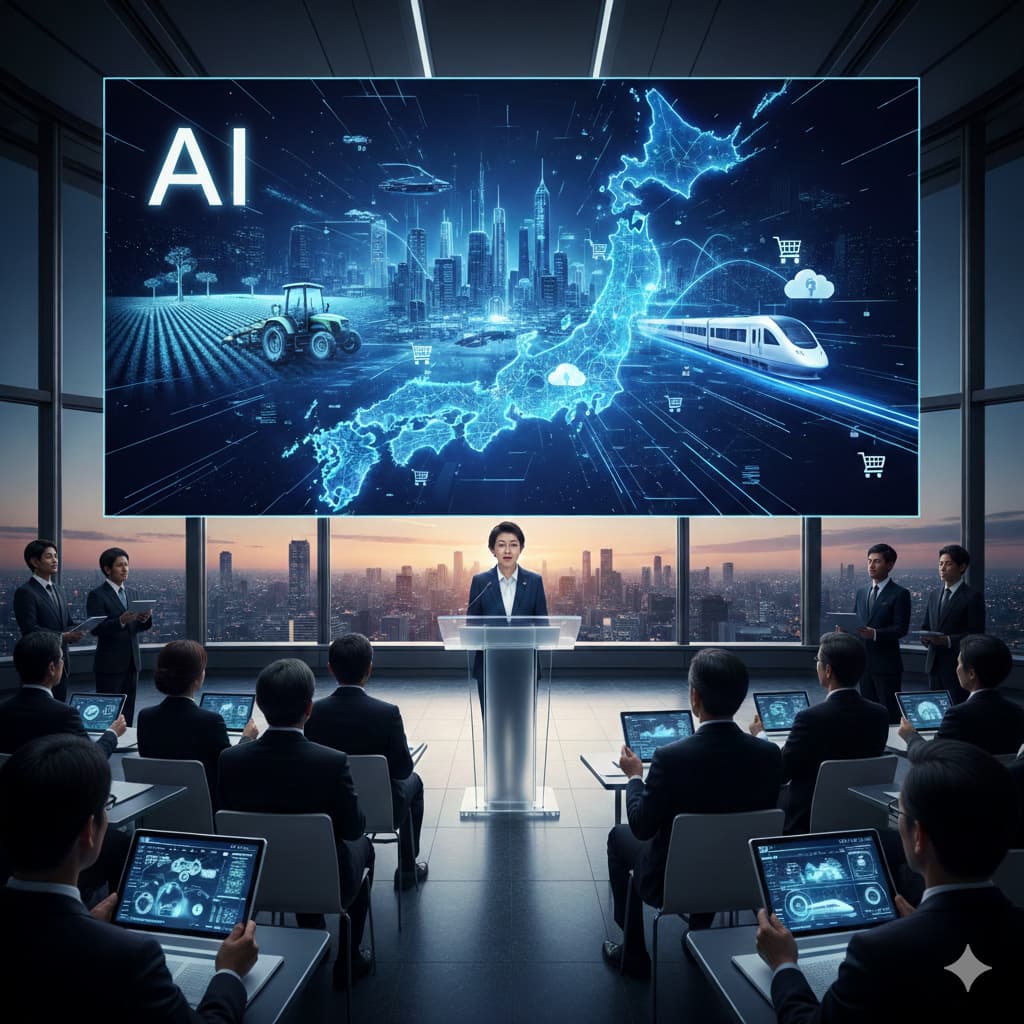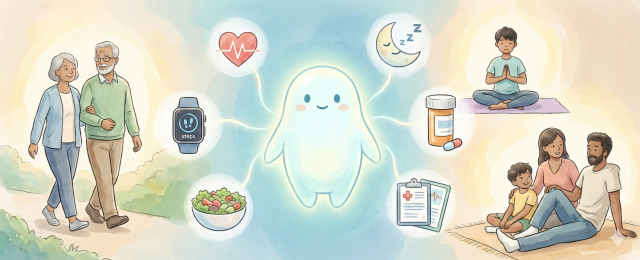先日、参議院選挙の熱い戦いが終わりました。各党が自身の公約をかかげ、支持者を得る為に様々な活動をしてきました。結果が良かった党も悪かった党もありますが、見ていると各党が「ブランド」を掲げてその価値の訴求に必死であったような気がします。 私は営業活動の際に、自社およびクライアントの方々の「ブランド」についてお話する事も多いので、「ブランド」戦略を成功させるためのポイントとは何か、ブランドの確立と認知戦略についての解説をまとめてみました。
1.ブランドとは何か
「ブランド」とは、単なる商品名やロゴマークのことではありません。ブランドとは、企業や商品、サービスなどが消費者からどのように認識され、選ばれるかを左右する「価値」や「イメージ」、「約束」を指します。顧客体験、提供する価値、理念などが含まれ、顧客や社会の心の中に存在する、特定の企業・商品・サービスに対する「信頼」や「好ましいイメージ」「意味のある連想」の総体です。
機能的価値
この製品は壊れにくい」「このサービスは便利だ」といった物理的な便益。
情緒的価値
「これを持っていると気分が上がる」「この会社は応援したくなる」といった感情的な便益。
これら二つの価値が積み重なり、顧客の頭の中に形成された「意味のある違い」こそがブランドの本質です。それは、無数の選択肢の中から「あなたを選ぶ理由」そのものと言えます。
2.ブランドの原点
ブランドの語源は、古ノルド語の「Brandr(焼印を押す)」に由来すると言われます。もともとは、放牧している家畜に自分の所有物であることを示すための「焼印」でした。
この焼印には2つの重要な意味がありました。
a. 所有者の識別:「これは誰の牛か」を明確にする。
b. 品質の保証:「あの焼印の牛は質が良い」という評判が生まれれば、品質保証の証となりました。
この「識別」と「品質保証」という機能は、現代のブランドにも通じる根源的な役割です。
3.ブランド価値の大小をきめるものは何か
ブランド価値(ブランドエクイティ)の大小は、究極的には「顧客の心の中のポジティブな認知の総量」によって決まります。具体的には、以下の要素で構成されます。
- ブランド認知度 (Brand Awareness)
- どれだけ多くの人に知られているか。単純な知名度だけでなく、「〇〇といえばこのブランド」と第一に想起されるか(純粋想起)が重要です。
- 知覚品質 (Perceived Quality)
- 顧客が主観的に感じる品質や優位性。「実際に高品質」であること以上に、「高品質だと信じられている」ことが価値となります。
- ブランド・ロイヤルティ (Brand Loyalty)
- 顧客がそのブランドを繰り返し指名買いしてくれる度合い。熱狂的なファンがいるブランドは価値が高いと言えます。
- ブランド連想 (Brand Association)
- そのブランド名を聞いたときに、どのようなイメージ(例:革新的、安心、高級、楽しい)が思い浮かぶか。この連想がポジティブで、かつ独自のものであるほど価値は高まります。感情的価値と表現することもできます。
- その他のブランド資産
- 特許や商標、強力な流通チャネルなどもブランド価値を支える資産です。
これらの要素が組み合わさり、価格プレミアム(他社より高くても売れる力)や市場シェア、収益の安定性といった財務的な価値に繋がります。

4.ブランド価値が高い企業たち
世界的なブランドコンサルティング会社Interbrand社のランキングなどを参考に、一般的にブランド価値が高いとされる企業を挙げます。知らない人はいないような会社たちです。
・Apple
・Microsoft
・Amazon
・Google
・Coca-Cola
5.これらの企業は何が認められているのか
これらの企業は、単に優れた製品やサービスを提供しているだけではありません。独自の「世界観」や「価値観」が認められています。
・Apple
「Think different」の精神に代表される革新性、創造性、洗練されたデザイン、そしてシームレスな顧客体験(エコシステム)。製品を持つことが自己表現の一部となるほどの強い情緒的価値を提供しています。
・Microsoft
ビジネスシーンにおける圧倒的な信頼性と生産性向上への貢献。近年はクラウドサービス(Azure)やAI分野でのリーダーシップにより、「未来の働き方を支えるテクノロジー企業」としての地位を再確立しています。
・Amazon
「地球上で最もお客様を大切にする企業」という理念を徹底的に追求する顧客中心主義。圧倒的な品揃え、迅速な配送、レコメンデーションなど、究極の利便性がブランド価値の源泉です。
・Google
「世界中の情報を整理し、世界中の人々がアクセスできて使えるようにする」という使命。情報へのアクセスの民主化を成し遂げた技術力と信頼性、そして「なくてはならない」存在感が認められています。
・Coca-Cola
1世紀以上にわたり「ハピネス(幸福感)」や「つながり」といった普遍的な感情に訴えかける一貫したメッセージ。製品そのもの以上に、ブランドが象徴するポジティブな世界観が世界中で愛されています。
6.ブランド価値を訴求するための手段。過去からの変遷
ブランド価値の訴求方法は、メディアと社会の変化と共に大きく変遷してきました。
- 過去(マスマーケティング時代)
- テレビCM、新聞・雑誌広告、ラジオといった四大マスメディアが中心。
- 企業から生活者への一方通行のコミュニケーション。「この製品はここが凄い」という機能的価値(USP: Unique Selling Proposition)を大々的に訴求することが王道でした。
- 変遷(インターネット黎明期〜)
- 公式ウェブサイト、Eメールマガジン、バナー広告などが登場。
- 限定的ではあるが双方向のコミュニケーションが可能に。企業は詳細な情報をウェブサイトに掲載し、顧客は能動的に情報を探しに行くようになりました。
- 現在(デジタル・SNS時代)
- SNS(X, Instagram, TikTok)、コンテンツマーケティング(ブログ、動画)、インフルエンサーマーケティング、コミュニティ運営など。
- 企業と生活者の対話・共創が当たり前に。企業が発信する情報よりも、第三者(他のユーザーやインフルエンサー)の口コミや評価が重視されるようになりました。顧客との継続的な関係構築(エンゲージメント)が最重要課題となっています。
7.近年のブランド価値訴求の傾向
現代のブランディングは、より本質的で人間的なアプローチが主流となっています。
- パーパス・ブランディング
- 「自社は何のために存在するのか(Purpose)」という企業の社会的な存在意義を明確に打ち出す手法。SDGsやESGへの貢献など、利益追求だけでなく社会課題の解決に取り組む姿勢が、特にミレニアル世代やZ世代からの共感を呼びます。
- ストーリーテリング
- 創業の想いや製品開発の裏側にある物語を語ることで、顧客の感情に訴えかけ、記憶に残りやすくします。単なるスペックの羅列ではなく、「なぜそれを作ったのか」という物語が共感を生みます。
- CX(顧客体験)の重視
- 商品購入時だけでなく、認知から購入後のサポートまで、顧客がブランドに接する全ての体験(CX)を設計し、一貫して質の高いものにすることで、長期的な信頼とロイヤルティを醸成します。
- コミュニティ形成
- ブランドのファンが集い、交流できるオンライン・オフラインの場を提供。ファン同士のつながりがブランドへの帰属意識を強め、熱狂的な支持層を育成します。
8.企業も選挙も同じ?選挙における「ブランディング」活動手段
選挙は、まさに候補者や政党という「ブランド」を有権者(顧客)に選んでもらう活動であり、マーケティング理論の応用が不可欠です。企業活動と同じだと思います。
- ブランド・アイデンティティの確立
- 理念・政策(コアバリュー)
- 「この国をどうしたいのか」という明確なビジョンと、それを実現するための具体的で分かりやすい政策。
- ビジュアル・アイデンティティ
- ロゴ、シンボルカラー、ポスターのデザイン、候補者の服装など、視覚的なイメージの統一。
- トーン&マナー
- 演説の語り口、SNSでの言葉遣い、メディア対応の姿勢など、人格を感じさせるコミュニケーションスタイル。
- 理念・政策(コアバリュー)
- コミュニケーションチャネルの最適化
- 伝統的メディア
- 街頭演説、個人演説会、テレビ討論などで、熱量や人柄を直接伝える。特に地域や高齢層に有効。
- デジタルメディアSNS(X, YouTube, Instagram等)
- 政策の分かりやすい解説(ショート動画など)、活動報告、有権者との直接対話、人格のアピール。ターゲット層に応じてプラットフォームを使い分ける。
- ウェブサイト/ブログ
- 詳細な政策や理念を掲載し、信頼性を担保する情報基盤。
- 口コミ/インフルエンサー
- 支持者が自発的に情報を拡散したくなるような「分かりやすく」「共感できる」メッセージを設計する。
- 伝統的メディア
9.まとめ
全ての企業は、価値の大小はあれどなんらかの「ブランド」を持ち掲げていると思います。企業の「ブランド価値」は、機能的価値と心理的価値の複合で形成され、企業が持つ商品・サービスに対する「信頼」や「好ましいイメージ」「意味のある連想」の総体です。
機能的価値は物やサービスの開発・改善で上げる事ができますが、心理的価値は支持を得るだけの価値をユーザーが認識して好意を抱く事が必要で、それが定着してはじめて「本物のブランド」となるのだと思います。
コアバリューがあったとしても、それを適切に伝える事ができなければブランドの価値は本来の評価を受ける事ができず、伝え方はとても大切な要素だといえます。SNSが普及している現在では、一方通行型のイメージ戦略では不十分で、ユーザーが感じる心理的価値を高め、ユーザーが持つ発信力をもって関係を強化してゆく取り組みが必要となっています。
認知手法が多様化する中でも、コアバリューが不明確であれば、いくら高く自社の価値を伝えようとしても、ユーザーの心理的価値は高まらず、ブランドの価値を上げる事はできないと思います。
お付き合いいただいているクライアントの方々は、皆様がそれぞれ持つ商品・サービスの機能的価値を持ち、これまで蓄積したユーザーからの評価・ストーリーがあります。それらを改めて正当に見つめなおし、Webが主役となってきているコミュニケーション手段を通じて、認知・評価されるためのお手伝いができればと思い、営業活動をしています。
また、クライアントの方々が我々のサービスを心理的価値をもって評価いただく事で、我々唐沢農機サービス・ビーズクリエイトの「ブランド」をより価値のあるものにしてゆくことができると思っています。
ビーズクリエイトへのお問い合わせはこちらからどうぞ。
https://www.bscre8.com/contact/
唐沢農機サービスでは、一緒に働く仲間を募集しています。
詳細情報はこちからからご確認ください。
https://recruit.karasawanouki.co.jp/